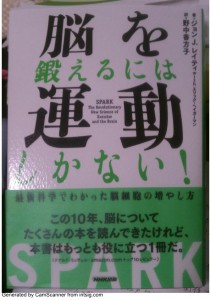始めは、ジャンプや開脚跳びなど余裕があったのに・・・
少しずつ高くなると・・・ 高い壁になっていく・・・
できるかな できないかな・・・
跳び降りるにもちょっと勇気がいる・・・
全身を使いながら子ども達のこころは、動いています^^
バランスも少しずつ難しくなっていきます。
バランスをとる環境や渡り方、講師の微妙な環境設定と
子ども達の発想を引き出す声掛けで、バランスをとる能力を高めていきます。
子どもの発想は豊かこんな渡り方もあるよ!!
と得意げに見せてくれます。
からだだけでなくこころ、脳はフル回転!!
何度も繰り返す事で、上達が目に見えます☆
登る、わたる、支える、握る、ぶら下がる、跳ぶ、走る、回る、転がる、避ける、柔軟性などなど様々な基本動作を引き出していきます。
また、基本動作が組み合わさった動きも意識し、複雑な動作ができるようにつなげていきます。
トレーニングや練習ではない、遊びの要素を高めた運動指導は、こころとからだを育みます!!